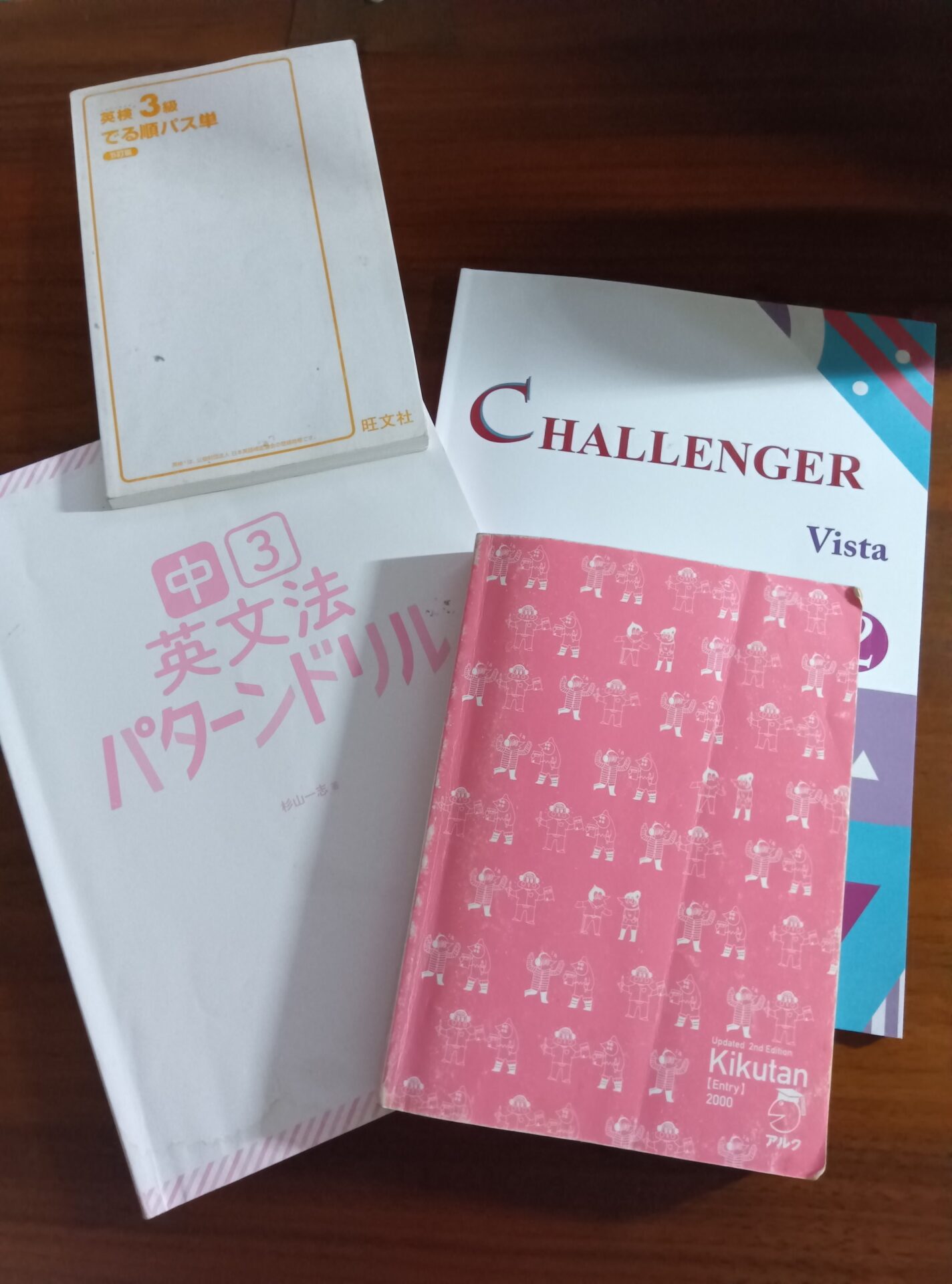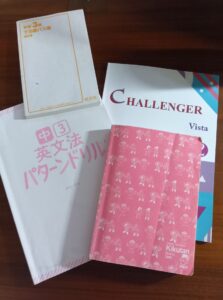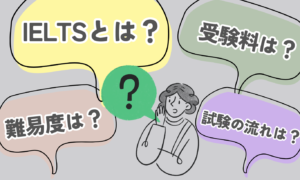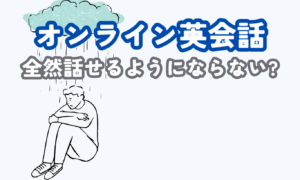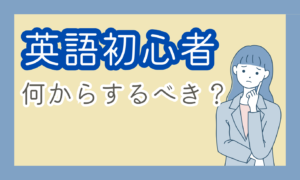自己紹介

英語学習仲間のみなさん、はじめまして。同じく英語学習者の延岡佑里子と申します。IT 企業に勤務しながら、副業で「行政書士 Science 事務所」を運営し、ライターも務めております。
・リアルタイムで英語学習を継続している人の体験談が読めます。
・英語学習継続「中」のメリットを知ることができます。
 佑里子
佑里子英語学習継続「中」のメリットを語った記事はあまり見かけませんね。



英語学習が大変で、そんなにメリットを感じてないのかな?



確かに学習は大変ですが、楽しさややりがいを感じる瞬間もありますよ。



どんな瞬間だろう?詳しく教えて!
本業の会社員では人事部に所属しており、課内の庶務係としてみなさんの仕事をサポートしています。副業の行政書士では、契約書作成や弁護士の先生・司法書士の先生のサポート、クライアントから依頼を受けて補助金申請業務のサポートなどをしています。
ライターとしては Amazon での電子書籍出版、また一時期 SPA!オンラインで執筆していたこともあります。出版社の翔泳社様のためにブックレビューを書いたり、東京報道新聞でも執筆活動をしたりしております。
こう自己紹介すると「忙しいですね」とみなさんおっしゃって下さいます。「忙しい」という言葉はどこか自己陶酔しているようで、あまり使いたくない感じがしますが、ありがたいことにタスクがたくさんあることは事実です。仕事の種類にこだわりはなく、どんな仕事でも好きなので、楽しんでやらせてもらっています。
また、私にはいくつかの属性があります。それは発達障害者(ASD)であり、精神保健福祉手帳も所持しているということです。加えて、親や元彼たちからの虐待を生き延びた虐待サバイバーであるということです。重すぎる話であるため、ここでエピソードを詳しく述べることはしません。
英語学習を継続している理由
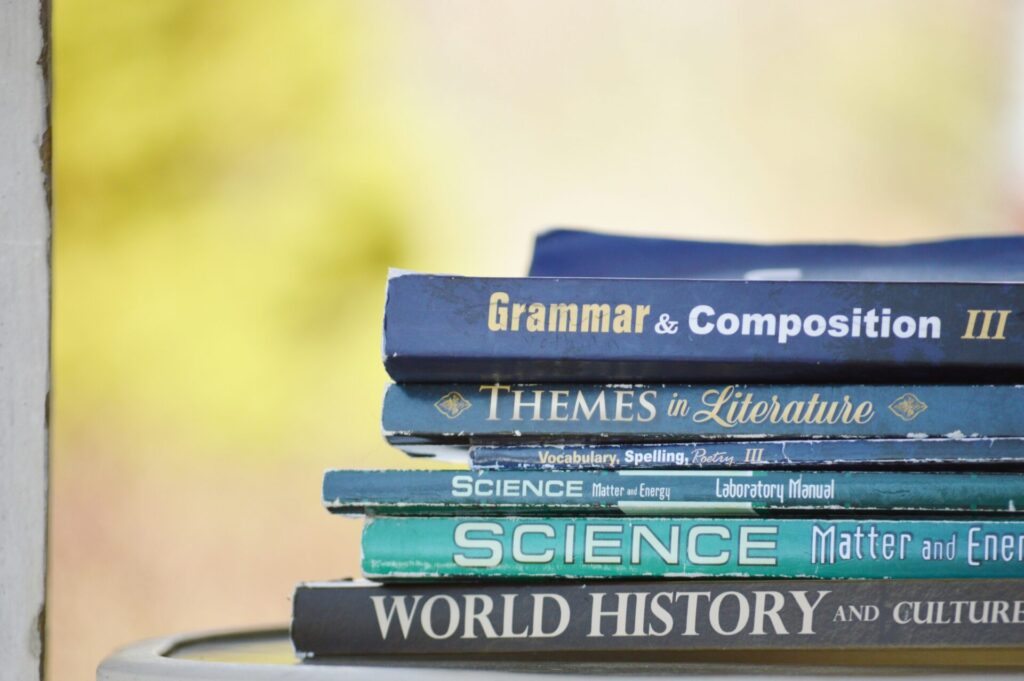
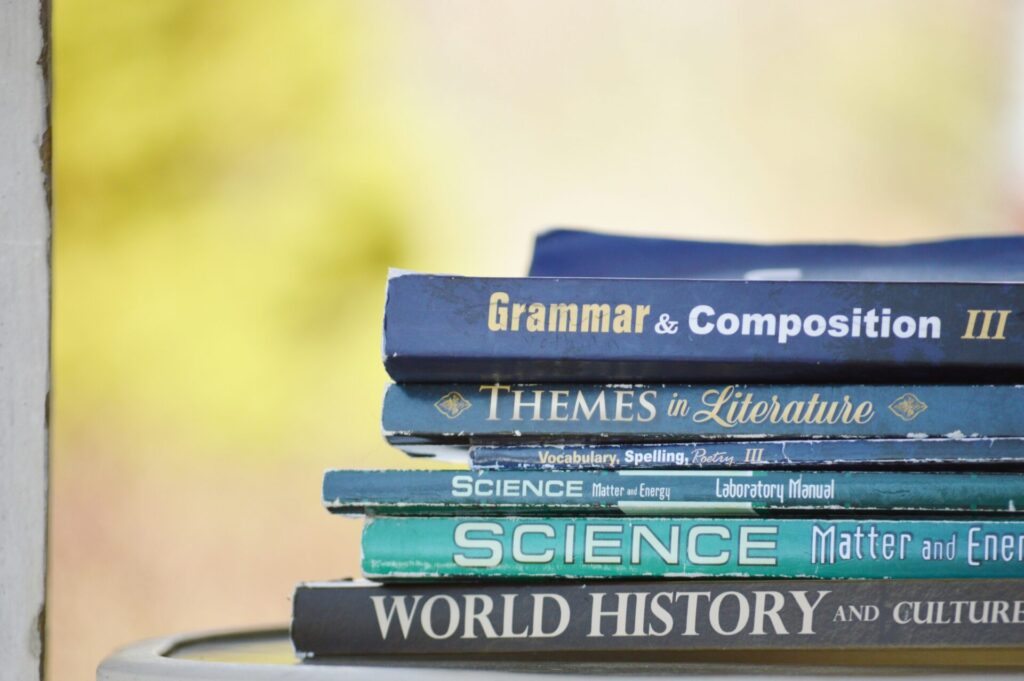
そんな暗い私がなぜ英語学習をしているのか、不思議に思われた方もいるでしょう。理由の一つは、「広い世界に飛び出すためには英語学習が必要だった」ということです。
虐待を受ける環境は閉塞的です。加害者も被害者も地位が固定化されていて、考えや心理が凝り固まっています。明確な悪意はないのかもしれません。ただ知らないことが多くて、少ない自分の考えに拘泥していてしがみついている。「ハンロンのかみそり」という言葉を思い浮かべた方もいるでしょう。
35 歳頃にようやく精神状態も落ち着き、ふとあたりを見回してみると広い世界があることに気が付きました。海外からの旅行客も日本にたくさん来ています。
私も海外旅行に行ってみたい、世界中の人と会話をしてみたい。そんな子どものような純粋な動機から、英語学習を継続しています。
二つめの理由は、「わからないことをわかるようになりたい、いろいろな知識を知りたい」といった素朴なものです。
上記のとおり、私は虐待を受けて育ちました。虐待の中には、暴力や暴言のほかに「家事を優先するよう言われ、勉強をさせてもらえない」といったものもありました。夏休み中、私は母が会社から帰ってくるまでの間に家事をすべて終わらせていなければなりませんでした。うっかりさぼると母は激怒して暴れ、教科書やランドセルを窓から庭へ放り投げました。
とてもではありませんが勉強をできる環境ではありませんでした。しかし前述のとおり私は 35 歳頃にようやく安全な環境を手に入れました。すると抑え込んでいた知的好奇心がふつふつと湧くようになりました。
過去を理由にして親を恨み、「なにもしない」ということも確かにできました。しかし私は知的好奇心を発揮してみたい、という欲望を素直に叶えてみることにしました。過去は変えられません。先ほどの「ハンロンのかみそり」の通り、親も大変だったのでしょう。失った時間を取り戻すことはできなくても、今、この瞬間から私は完全に自由です。やりたいことはなんだってできま
す。
ほかにも英語学習を継続している理由はいろいろあるのですが、大きな理由はこの二つです。
私の簡単な英語学習歴


もともと言語が好きで、外国語に興味があった。そんな漠然とした動機のもと、私は 2024 年1月ごろより英語学習を開始しました。2025 年 7 月現在、大体 1 年半程が経ったこととなります。
2024 年の春先に受けた TOEIC の結果は 250 点でした。リスニングが聞き取れない、英語長文がわからない。しかし不思議と英語を完全に嫌いになることはなく、約1年間、オンライン英会話を週1で継続しました。
本当は毎日レッスンを受けたいのに、勇気が出ずに躊躇してしまい、週1回受けるのが精いっぱいでした(これでもかなり思い切ったほうです)。外国人講師の先生方はみなさん優しい方ばかりなのに、どうしても緊張してしまっていました。
やがてどうせ週1回のレッスンなら対面式で学習しようと、英会話スクールの ECC に切り替えました。2025 年 3 月頃のことです。7 月現在、週 1 回 50 分のグループレッスンを継続できています。
英語学習継続のメリット


現段階で享受できている、英語学習継続のメリットがいくつかあります。
メリット①海外からの旅行客への道案内に成功
先月のことですが、東京駅で海外からの旅行客夫婦に道を聞かれ、なんとか回答できたということです。ご夫婦の一人が車いすユーザーだったのですが、とっさにエレベーターを探して見つけることができました。無事案内することができたときの感激はひとしおでした。
なぜ英語で道案内ができて嬉しかったかというと、「Thank you」と感謝をされたからです。
どんなに英語が苦手な人でも「Thank you」は知っているでしょう。「ありがとう」といったあたたかい感謝の言葉を通して、世界と交流できた瞬間でした。英語学習を継続しよう、といったモチベーションにもつながりました。
メリット②英会話スクールのレッスンが単純に楽しい
メリットの 2 つめは、英会話スクールのレッスンが楽しいということです。
もちろん最初から楽しかったわけではなく、慣れない学習に最初は疲弊していました。レッスンが終わると文字通りヘトヘトになっていました。
しかし 3 か月程経過した今では、レッスンの雰囲気に慣れたためか講師やほかの生徒と交流できるだけの余裕ができてきました。また講師の英語も断片的に理解することができるようになってきました。
これは英会話スクールを 3 か月受講したことももちろんですが、これまでの断片的なオンライン英会話受講、引いては中学・高校・大学での英語学習の総和のように感じています。途中休んだことがあっても、英語学習を継続したことは意味があったのだと思います。
潜在学習は少しずつ進んでいて、学習を継続する限り今後も蓄積されていくでしょう。
すべての学習は意味があるのです。学習継続することの意義をここに見出すこともできます。
メリット③世界とつながれている、世界を垣間見ているかのような感覚がある
先日、『THINK AGAIN 発想を変える、思い込みを手放す』(三笠書房)という本を読みました。この本の趣旨は、考えを変えること、再考すること、考えの誤りに気づくことを「楽しもう」といったものでした。
少しずつではありますが英語学習を継続することによって、私は世界とつながれているかのような感覚があります。
世の中の主流の考え方も、〝絶対〟ではない。同時に、私の考えも変わっていく。
英語の文章で書かれている内容を理解することによって、私の考えも少しずつ変わっていったり、新たな観点を手に入れたりすることができます。それが途方もなく面白いのです。
もっと劇的に言えば、英語学習は私の「脳」の神経ネットワークを「つくりかえる」ということだと思っています。英語学習は自室の机の上だけでは完結せず、ECC で講師と交流したり、通勤電車の中で英語の YouTube を観たりします。将来的には海外旅行も行くでしょう。ゆくゆくは海外移住だってするかもしれません。
つくりかえた脳内を世界と接続させると、刺激や反応の応酬があります。このワクワクするかのような躍動感が、私とって英語学習のメリットです。
なにもかもが英語学習のメリット


英語学習継続のメリットとしては、上記はやや抽象的だったと思います。
英会話スクールの宣伝などで普通語られる英語学習のメリットとは、例えば「TOEIC で 800 点を達成し、憧れの海外支社に転勤できた」とか、「翻訳者としてのキャリアをスタートさせた」とか、「社内でも『英語が得意な人』と認識され、海外の取引先との交渉の仕事が回ってきた」などであり、こちらのほうが容易にイメージしやすいでしょう。
もちろんこれらも大切なメリットではあります。しかし、英語学習継続によってこれらのメリットを享受するには、「やや時間がかかる」ということも覚えておいたほうがよいでしょう。
上記のような、「海外支社に転勤」といった華々しい成果だけを「英語学習継続のメリット」とみなしてしまうと、英語学習の道中はつらいものとなります。私が挙げたように、自分の中に英語学習のメリットを探してみるのはいかがでしょうか。
事実、目には見えなくとも英語学習を継続している私たちの「脳」は確実に反応しており、神経細胞は英語学習に反応して新たな軸索を伸ばしているのです。
英語学習によって「脳」がつくりかえられている。こう考えると私は非常にワクワクします。これが私にとっての英語学習継続の最大のメリットです。
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は「英語学習を継続するメリット3選」というテーマでお話をしました。
もちろん英語学習のメリットはこれ以外にもたくさんあるでしょう。あなたが感じている英語学習を継続するメリットも、ぜひ教えてください。
英語学習仲間として、ぜひ一緒に頑張っていきましょう。